多くの人に愛されてきた「リプトン ミルクティー」が、2022年に突然販売終了となったことをご存じでしょうか?日常の中に溶け込んでいたあの味がなぜ消えたのか、気になって検索された方も多いはずです。本記事では、販売終了の背景や本当の理由、リニューアル品「ロイヤルミルクティー」との違い、そして“たった1年”での異例の復活劇までを、時系列で丁寧に解説しています。さらに、667件の再販要望や、SNSで話題となったアニメ「667通のラブレター」の裏側、さらにはコカ・コーラの伝説的マーケティングとの共通点もご紹介。この記事を読むことで、「なぜ終了し、なぜ戻ってきたのか?」という疑問にしっかり答えが見つかります。
リプトン ミルクティーはなぜ販売終了になったのか?
販売終了の発表とその時期(2022年3月)
結論からお伝えすると、「リプトン ミルクティー」は2022年3月に販売終了となりました。
それまで長年親しまれてきた紙パックタイプの定番ミルクティーが、突然スーパーやコンビニの棚から姿を消したことで、多くのファンが困惑しました。
なぜこのような決断に至ったのかというと、森永乳業が「リプトン ロイヤルミルクティー」へのブランド刷新を図ったからです。
1989年から続いてきた人気シリーズを、より本格的な味へとリニューアルするため、旧商品を終売する判断が下されました。
以下の表で概要を整理します。
| 項目 | 内容 |
| 終売日 | 2022年3月 |
| 対象商品 | リプトン ミルクティー(紙パック) |
| 販売者 | 森永乳業 |
| 刷新後の商品名 | リプトン ロイヤルミルクティー |
| 主な変更の理由 | 商品リニューアルによる戦略的判断 |
新しいロイヤルミルクティーへの期待があった一方、突然の終売発表は、長年のファンにとって受け入れがたいものでした。
リニューアルされた「ロイヤルミルクティー」の特徴と狙い
「ロイヤルミルクティー」への刷新は、味わいや品質の向上を目的とした前向きな改革でした。
森永乳業は、それまでの「紅茶飲料」ではなく「乳飲料」へと分類を変え、本格的な味わいを追求しました。
具体的には以下のような改良が加えられています。
- 使用する茶葉を5%増量
- 乳固形分を1.5倍以上に強化
- 紙パックのデザインも刷新し、高級感を演出
このリニューアルには、「ミルクティーをより本格的に楽しみたい」という層を取り込む意図がありました。
また、離脱したかつての愛飲者や、新規の20~30代層の獲得も狙っていたと推察されます。
しかし、結果的にこの戦略がファンの心に空白を生み、のちに「リプトン ミルクティー」の“旧発売”という異例の展開へとつながるきっかけとなりました。
リプトン ミルクティーが販売終了になった本当の理由
学生人口減少・紙パック市場の縮小
販売終了の背景には、単に味を変えたかったというだけでなく、飲料業界全体の構造的な変化も影響しています。
特に深刻だったのが、学生数の減少と紙パック市場の縮小傾向です。
以下のようなデータがあります。
- 文部科学省の統計によれば、2020年代以降、10代の人口は年間数万人単位で減少
- 紙パック飲料の市場規模も、2010年代後半から右肩下がり
「リプトン ミルクティー」は長年、「学生の定番ドリンク」として親しまれてきました。
そのため、購買層である学生が減るという現象は、売り上げに直接的な影響を与えました。
しかも、若者の間ではペットボトルや缶タイプの飲料が主流となり、紙パックの相対的価値が下がりつつあったのも事実です。
コロナ禍による生活スタイルの変化
もう一つ見逃せないのが、新型コロナウイルスの影響です。
コロナ禍によって在宅勤務やリモート授業が広がり、「通勤・通学中に飲むドリンク」という需要が激減しました。
とくに紙パック飲料は、「片手でサッと飲める」「コンビニで買ってその場で飲む」といったシーンに強い商品です。
ですが、感染症対策で外出が制限される中、その「シーン」自体が失われてしまいました。
こうした環境の変化が、売上の低迷に追い打ちをかけたといえます。
森永乳業のマーケティング的挑戦とその代償
森永乳業が「リプトン ロイヤルミルクティー」への刷新に踏み切ったのは、単なる商品改良ではありません。
これは、マーケティング戦略としての大きな挑戦でした。
企業にとってロングセラーブランドを刷新するというのは、かなりのリスクを伴う決断です。
森永乳業はそれでも、品質向上と新規ユーザー獲得を見込んで改革を実行しました。
ところが、旧商品のファンからは予想を超えるほどの反発が起こり、わずか1年で旧商品の再販へと舵を切ることになります。
このように、商品リニューアルは「挑戦」でありながら、「代償」を伴うものでもあったという事実が浮かび上がります。
なぜ「ロイヤルミルクティー」ではファンが納得しなかったのか?
味の変化よりも“思い出”の喪失
ファンがロイヤルミルクティーに馴染めなかった一番の理由は、味の変化ではありません。
問題は、長年親しんできた“記憶”が消えたように感じられたことにあります。
「他のじゃダメなんです」「ミルクティー人生が終わった」など、消費者相談室に届いた667通の意見には、味そのものを批判するものは多くありませんでした。
多くが、「昔ながらのリプトン ミルクティーが好きだった」という感情的な訴えだったのです。
ミルクティーは、ただの飲み物ではなく、青春の一部や日常の象徴でした。
それがある日突然なくなったことで、心にぽっかりと穴があいたように感じた方が少なくなかったのです。
購買層は「学生」ではなく「元学生」だった
一般的には「学生の飲み物」というイメージがありますが、実際に購入していたのは20〜50代の社会人でした。
これは、かつて学生時代にリプトン ミルクティーを愛飲していた人たちが、社会人になっても習慣的に買い続けていたからです。
以下のような購買者層が主力でした。
- 20代後半:学生時代の味として定着
- 30代:日常の癒しアイテムとして継続購入
- 40〜50代:仕事中や休憩時に一息つける存在
つまり、マーケティング的には「青田買い戦略」が成功していた商品だったのです。
だからこそ、その“原点”を失ったことが、過去を生きる大人たちに強いショックを与える結果となりました。
紙パックの質感すら“記憶”だったという事実
「紙パックを握る感覚まで覚えている」
こうした声が実際に届いていたことからもわかるように、包装形態までもが愛着の対象となっていました。
リプトン ミルクティーの紙パックは、手にフィットする独特のフォルムと紙の温もりが特徴でした。
長年の飲用体験によって、それは単なる容器ではなく、感情や記憶と強く結びついていたのです。
こうした「五感」に訴えるブランド体験は、数字では測れませんが、消費者との深い絆を作る大切な要素です。
リプトン ミルクティー再販に至った3つの決定的要因
667件の要望が「史上最多」だったインパクト
リプトン ミルクティーが再販された最大の理由は、667件にもおよぶ消費者からの再販要望がメーカーに届いたためです。
この件数は森永乳業の歴史の中で最多のご意見件数とされており、前例のない事態でした。
なぜこの数が重要なのかというと、通常、販売終了した商品に対する意見が数十件程度で収まることが多いためです。
ところが今回は、2022年4月〜9月のたった半年間で667件もの要望が寄せられ、1日に40件以上届いた日もありました。
以下に数字のインパクトを一覧にまとめます。
| 項目 | 内容 |
| 意見総数 | 667件 |
| 期間 | 2022年4月〜9月(6か月) |
| 多かった日の件数 | 1日40件以上 |
| 森永乳業における記録 | 過去最多のご意見件数 |
| 意見の多くが再販希望 | 味や思い出に関する強い訴え |
これほどの熱意を見た森永乳業は、リニューアル後の戦略を変更するほどの強い衝撃を受けました。
顧客の声が企業の方針すら動かした、非常に珍しいケースといえます。
棺桶に入れてほしい…ファンの“異常な愛”
再販を後押ししたもう一つの要因は、ファンの感情の強さでした。
単なる「おいしい飲み物」という次元を超え、「人生に寄り添う存在」としてのリプトン ミルクティーへの愛情が爆発していたのです。
実際に森永乳業のお客様相談室には、以下のようなコメントが数多く届いています。
- 「この悲しみをどこにぶつければいいのかわかりません」
- 「生きる希望がなくなりました。眠れません」
- 「私のミルクティー人生は終わった」
- 「死ぬときは棺桶に入れてほしい」
中でも「棺桶に入れて」という言葉は、DIMEの記事でも取り上げられ、象徴的なエピソードとなりました。
このような情熱的なメッセージは、ブランドにとって何よりの財産です。
マーケティングの教科書には載っていない、“ファンとの絆”の強さが再販の決定を後押ししたことは明白です。
1年という短期間での“異例の決断”
もう一つ注目すべきは、終売からわずか1年で再販されたというスピード感です。
一般的にリニューアルや終売は中長期的な戦略として実施されるため、1年未満での方針転換は非常に異例です。
ロイヤルミルクティーとして生まれ変わったのが2022年3月、再販されたのが2023年3月。
この1年間に、森永乳業は消費者の声を真摯に受け止め、改めて元の味を「旧発売」として市場に戻しました。
リニューアルから終売・再販までの流れを以下にまとめます。
| 年月 | 出来事 |
| 2022年3月 | リプトン ミルクティー終売 → ロイヤルミルクティー発売 |
| 2022年4〜9月 | 再販要望が殺到(667件) |
| 2023年3月 | リプトン ミルクティーが「旧発売」として復活 |
この迅速な対応には、森永乳業の柔軟性と消費者への誠意が表れているといえます。
企業にとっては痛みを伴う決断であっても、ファンとの信頼を守る行動こそが、長期的なブランド価値を高めるのです。
なぜ販売終了のニュースがこれほど話題になったのか?
「希少性」と「損失回避」の心理
話題になった背景には、人間の行動心理が深く関係しています。
中でも「希少性の原理」と「損失回避の原理」の2つが強く働いていました。
- 希少性の原理:手に入りにくくなると価値を感じる傾向
- 損失回避の原理:得るよりも「失うこと」に強く反応する傾向
特に「慣れ親しんだ味が突然なくなる」という出来事は、損失のインパクトを増幅させます。
それまで意識せずに買っていたミルクティーが消えることで、「こんなに大切だったんだ」と気づく人が続出しました。
販売終了というニュースに、無意識の心理的反発が加わり、SNSでも大きな話題になったのです。
青春時代に根付いたブランドの力
リプトン ミルクティーは、ただの飲料ではありませんでした。
多くの人にとって、それは中高生や大学生時代の青春の一部でした。
- 放課後のコンビニで買って飲んだ
- 試験前に気合を入れるために手に取った
- 恋人とシェアした思い出がある
こうした個人の記憶に深く根ざしているブランドは、一度消えると感情的な反発を招きやすくなります。
思い出と共にあった味が消えることに、「自分の青春が切り取られた」と感じる人が多かったのです。
このブランド力こそが、話題化の大きな原動力となりました。
SNS時代ならではの炎上→注目の構図
販売終了のニュースが拡散されたもう一つの理由は、SNS時代特有の「炎上型バズ」にあります。
特にTwitter(現X)やInstagramでは、「#リプトンミルクティー復活して」などのハッシュタグで声が次々と共有されていきました。
次のような構図が見られました。
- 販売終了が報じられる
- ファンが怒りや悲しみを投稿
- 他のユーザーが共感・拡散
- メディアが取り上げて報道
- さらにSNSで注目される
このサイクルが短期間で何度も繰り返され、話題が雪だるま式に膨らんでいったのです。
炎上のように見える動きが、最終的にはブランド価値を再確認する機会につながりました。
リプトン ミルクティー復活はどのようにして実現したのか?
「旧発売」宣言と謝罪メッセージ
再販時に森永乳業が行った演出は、ただの再発売ではありませんでした。
彼らはこの復活を「旧発売」と名づけ、ファンに向けて感謝と謝罪のメッセージを添えました。
パッケージには以下のような文言が記載されました。
「待たせて、ごめん。あの日、勝手に味を変えてごめんなさい。
あなたが“もとの味に戻して”と手紙をくれたから。
森永乳業史上最多のご意見が届いたから。
もとの味に戻しました。
だからこれは“新発売”ではなく、“旧発売”。」
このような真摯な姿勢とユーモアのある表現が、多くの人の心を打ちました。
感謝と謝罪をきちんと伝えることで、ファンとの信頼関係がより強固になったのです。
アニメ「667通のラブレター」に込めた想い
復活のプロモーションの一環として、森永乳業は短編アニメ「667通のラブレター」を公開しました。
タイトルは、実際に届いた要望の数をそのまま使っています。
物語は以下のような内容です。
- 主人公トーマと唯が高校最後の春を迎える
- 突如現れた転校生ルミ(ロイヤルミルクティーの象徴)により、2人の世界が分断
- トーマと唯は、消えた相手に667通の手紙を送り続ける
このストーリーは、消費者が抱いた「消えてしまった大切な存在」への想いをアニメで可視化したものでした。
2日間で100万再生を突破するなど、大きな反響を呼びました。
新規ファンと既存ファンをつなぐプロモーション
復活後のマーケティングは、単なる“懐かしさ”を訴えるだけで終わりませんでした。
「旧発売」という表現に象徴されるように、既存ファンのノスタルジーを大切にしながら、新規ファンにも届くような展開が行われました。
具体的には以下のような戦略がとられました。
- SNSを中心とした口コミ拡散施策
- アニメーションを活用したストーリーマーケティング
- コンビニ限定キャンペーンなどの展開
このように、「思い出の商品」として終わらせず、再び手に取ってもらう理由を設計したことで、復活は一過性で終わらず、現在も安定した人気を維持しています。
販売終了から復活までのタイムラインまとめ
2022年の終売から2023年の復活までの全過程
リプトン ミルクティーは、終売から復活までの1年間に、異例ともいえる数々の出来事を経て再び店頭に戻りました。
この流れを振り返ることで、消費者の声がどれだけブランドを動かせるかが明らかになります。
まずは、時系列で全体像を整理します。
| 時期 | 出来事 |
| 2022年3月 | 「リプトン ミルクティー」終売(ロイヤルミルクティーへ刷新) |
| 2022年4〜9月 | 再販要望が殺到(合計667件) |
| 2023年3月 | 「旧発売」として再登場、元の味で完全復活 |
| 2023年3月下旬 | アニメ「667通のラブレター」公開、再生数100万回突破 |
この一連の動きは、単なる商品のリニューアルにとどまらず、ブランドとファンの信頼関係を再構築する過程だったといえます。
とくに注目すべきは、たった1年でリニューアルを撤回するというスピード感と柔軟性です。
消費者の意見を「記録的件数」で受け止め、それを誠実に反映した判断こそが、森永乳業のブランド力の源となりました。
ブランド戦略としての評価とマーケティング的教訓
この一連の流れは、ブランドマーケティングの教科書にも載るべき貴重な事例です。
リニューアルによる新規顧客の開拓と、既存ファンの感情的なロイヤルティ。この2つをどうバランスさせるかという問いに、実例で答えを示したのが今回のケースです。
重要な学びは以下の3点に凝縮されます。
- 「本格派路線=正解」ではない:味の向上が必ずしも支持されるとは限らない
- 定番商品の変更は想像以上のリスクを伴う:習慣と感情に結びついた商品には特別な注意が必要
- 顧客の声に即応するスピード感が信頼につながる:1年以内の再販は誠実さの象徴だった
リプトン ミルクティーの復活劇は、見えにくいブランド価値の重要性を再認識させ、数字に表れない「絆」の強さを証明した形となりました。
コカ・コーラ「ニューコーク騒動」との共通点
世界の名ブランドも誤算を経験している
実は、リプトンのケースとよく似た出来事が過去にも起きています。
1985年、アメリカのコカ・コーラ社が「ニュー・コーク」を発売したときの騒動です。
当時、ペプシとの競争に危機感を抱いたコカ・コーラは、長年親しまれていた元の味を変更し、「新しい味」のコーラを全面的に展開しました。
しかし、結果は大失敗。全米で大反発を受け、わずか3か月後に「コカ・コーラ・クラシック」として元の味を復活させることになりました。
| ブランド | 変更内容 | 結果 |
| コカ・コーラ | 元の味を終了 → ニュー・コーク発売 | 3か月で旧味が「クラシック」として復活 |
| リプトンミルクティー | 紙パック終売 → ロイヤルミルクティー | 1年で「旧発売」として復活 |
どちらも「味を良くしたつもり」で変更したにも関わらず、顧客に受け入れられなかった点が共通しています。
そして、どちらの企業もファンの声に耳を傾け、スピーディーに対応したことで、ブランド価値をさらに高める結果につながりました。
顧客の声がブランド価値を“見える化”した瞬間
どちらの騒動にも共通していたのは、「顧客の声」が企業にとってのブランド資産の見える化を果たしたという点です。
日常のなかで当たり前のように存在していた商品が消えたとき、人々が初めてその価値に気づき、声をあげました。
特にリプトン ミルクティーに届いた意見は、ただの要望ではありませんでした。
- 棺桶に入れてほしい
- 他のミルクティーでは代わりにならない
- 思い出が詰まっているから戻してほしい
こうした強烈なメッセージが、森永乳業に「数字では測れないブランドの価値」を突きつけました。
顧客の感情に根ざしたブランドは、ロジックや売上以上の力を持つと証明された瞬間でした。
結論:なぜ「リプトン ミルクティー」は販売終了してはいけなかったのか?
単なる飲み物ではなく、記憶と結びついたブランド
結論として、リプトン ミルクティーは「ただの飲み物」ではありませんでした。
それは多くの人にとって、学生時代や青春の日々と深く結びついた存在でした。
人は、何気ない日常の習慣にも強い感情を抱きます。
コンビニで見かける安心感、授業の合間に飲んだひととき、好きな人とシェアした記憶。そうした体験が、紙パックの中に詰まっていたのです。
だからこそ、急な終売は“自分の一部”が失われたように感じられ、悲しみや怒りの声が広がりました。
味ではなく、記憶に根ざした価値がリプトン ミルクティーの本質だったのです。
森永乳業が得た“見えない価値”と今後の展望
今回の出来事は、森永乳業にとって数値化できない価値の重要性を可視化した経験となりました。
ブランドは売上だけでなく、人との絆や記憶との接点によって支えられています。
その結果として得られた教訓は次の通りです。
- リニューアル前に「ブランドの感情的資産」を調査することの重要性
- 顧客の声を「戦略情報」として活用する姿勢
- ブランドに関わる全ステークホルダーへの丁寧な説明と配慮
今後、森永乳業が新たなブランドを構築していく上で、この経験は大きな財産になります。
再販という選択は、単に“戻す”という行動にとどまらず、ブランドを再発見するきっかけとなりました。
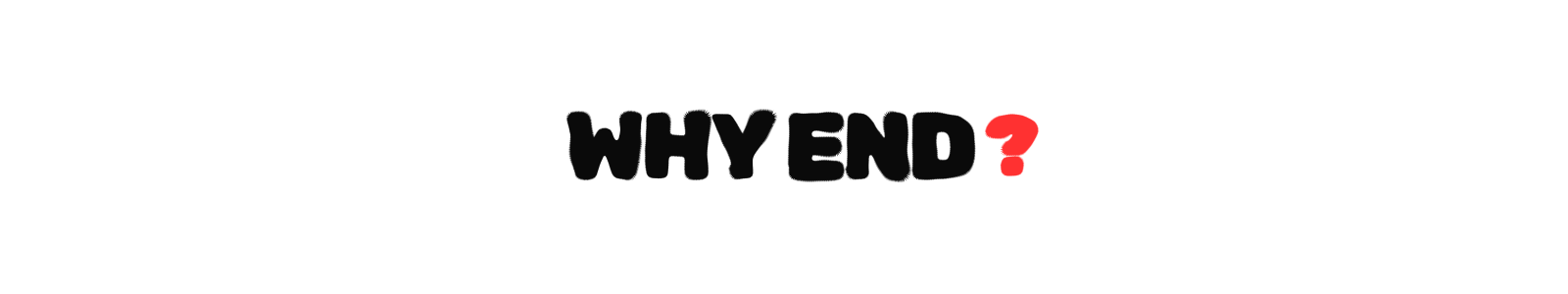



コメント